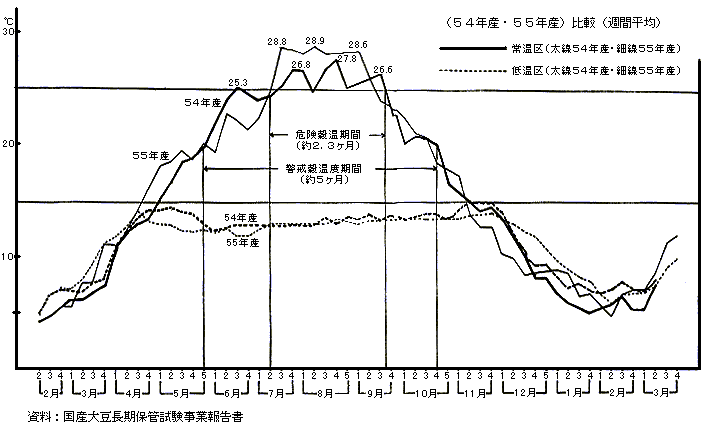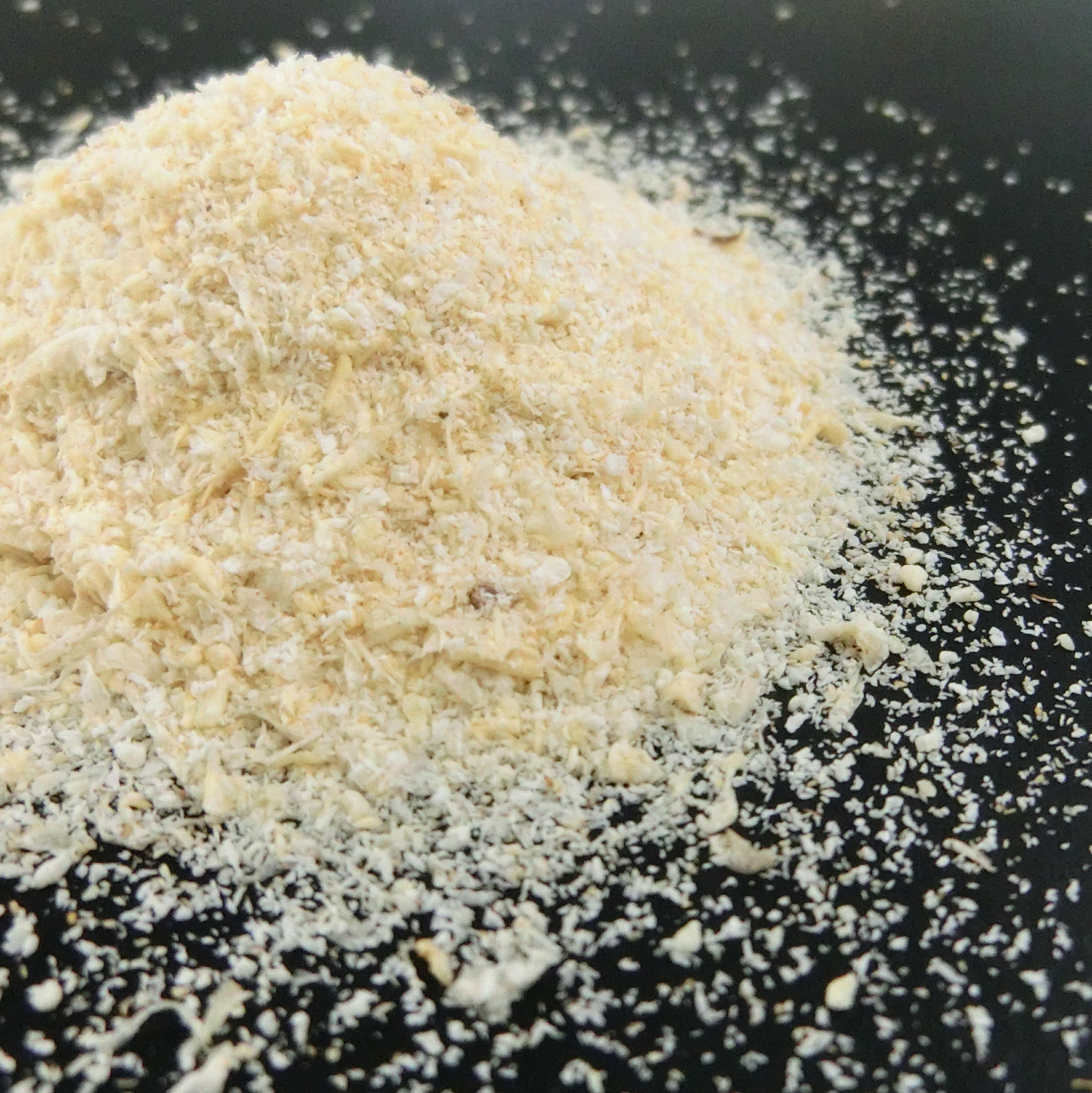大豆の流通・保管
作物である大豆も保存・流通により、品質が大きく劣化することがあります。
特に保存期間が長くなるほど、微生物、害虫の発生、原料大豆の水分含量変化、油脂の酸化、大豆タンパク質の変性等が起こります。
そのため、保存温度の管理が重要となります。
弊社では、お客様により品質の良い大豆をお届けするため、流通・保存方法にもこだわっています。
流通のこだわり
「小ロットから大豆が欲しい」とのお客様のご要望に応じて、
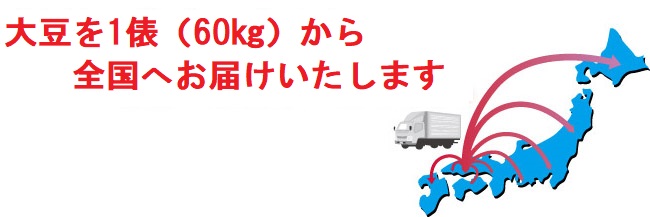
保管温度のこだわり
品質の劣化には、大豆の保管温度が大きく関わってきます。
そのため、弊社の大豆保管倉庫は、

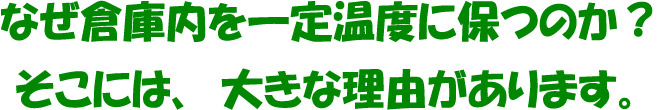
貯蔵条件による成分の変化
【農林水産省HPより引用】
大豆の貯蔵条件が品質に及ぼす影響についての研究が十分されているとは言い難いのですが、昭和53年に行われた平らの研究結果を紹介します。
○貯蔵条件
貯蔵試験は、自然乾燥・加温乾燥など乾燥条件の異なる水分約15%の大豆を使用し、貯蔵は2月から1月までの12ヶ月間、庫内温度15℃と30℃で相対湿度65%と75%及び常温(東京)の5条件下で行った。
なお、この貯蔵条件の設定理由は、15℃は現在穀類の低温倉庫で用いられている温度条件であり、30℃は夏期に長期間にわたり起り得る条件である。
また、相対湿度65%と75%は、大豆の平衡水分が10%~15%の範囲に入り得る湿度を考慮した条件である。
| 庫内温度 | 相対温度 | 発芽率 | 蒸煮大豆重量増加率 | 蒸煮大豆硬さ | その他の加工適正 |
| 15℃ | 65% | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70% | △ (加湿乾燥の場合低下) |
○ | ○ | ○ | |
| 30℃ | 65% | × | × | × | × |
| 70% | × | × | × | × | |
| 常温(夏期) | - | × | × | × | × |
上図で示すように、大豆の品質は貯蔵温度・湿度により大きく変化します。 そのため、弊社では大豆を定温保存し、品質の劣化を抑えています。
| 原料大豆の 水分含量変化 (貯蔵開始時 13%~15%の範囲) |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料大豆の発芽率 | 一般に、発芽率は生命力や鮮度判定の指標となる項目として重要視されており、大豆への乾燥処理条件による差異が大きい。また、発芽率が低下すると大豆を浸漬したとき溶出固形分が増加する。
|
|||||||||||||||
| 蒸煮大豆の 重量増加率 蒸煮大豆の硬さ |
蒸煮大豆の重量増加率の変化は、原料大豆に対する味噌、納豆、煮豆の収率の指標となることから重要。
|
|||||||||||||||
| その他加工適正 | 試験では、この他吸水率、浸漬液中の溶出固形物とタンパク質の増加、タンパク質抽出率の低下、豆乳のpHの低下、水分含量の増加、色調の劣化を確認。
|
|||||||||||||||
微生物、害虫の発生等に起因する品質低下
品質劣化の要因は、梅雨期及び夏期高温期における環境条件に起因します。
特に貯蔵庫内の温度が20℃を超えると呼吸作用が旺盛となるため、成分の損耗が起こり、また、貯蔵庫内の温度が25℃を超えるくらいから病害虫の繁殖が最盛期を迎えると言われています。
下図は東京都内の倉庫における大豆の穀温の変化をグラフ化したものです。穀温が20℃を超えるのが5月末から10月中旬で、この時期の温度管理が悪いと害虫発生、大豆品質劣化等が起こります。